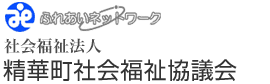指定居宅介護支援事業の概要は次のとおりです。
居宅介護支援事業(ケアマネジャー)
ケアマネだよりはこちら ↓
ケアマネだより 32号(pdf)(2023.8) 最新号
ケアマネだより 31号(pdf)(2023.3)
ケアマネだより 30号(pdf)(2022.10)
ケアマネだより 29号(pdf)(2022.3)
ケアマネだより 28号(pdf)(2021.11)
ケアマネだより 27号(pdf)(2021.3)
ケアマネだより 26号(pdf)(2020.9)
ケアマネだより 25号(pdf)(2020.1)
ケアマネだより 24号(pdf)(2018.8)
ケアマネだより 23号(pdf)(2018.1)
ケアマネだより 22号(pdf)(2017.9)
ケアマネだより 20号(pdf)(2016.8)
ケアマネだより 19号(pdf)(2016.1)
ケアマネだより 18号(pdf)(2015.7)
ケアマネだより 17号(pdf)(2015.1)
ケアマネだより 16号(pdf)(2014.7)
ケアマネだより 15号(pdf)(2014.1)
ケアマネだより 14号(pdf)(2013.7)
ケアマネだより 13号(pdf)(2013.1)
ケアマネだより 12号(pdf)(2012.7)
ケアマネだより 11号(pdf)(2012.1)
ケアマネだより 10号(pdf)(2011.10)
ケアマネだより 9号(pdf)(2011.7)
ケアマネだより 8号(pdf)(2011.4)
ケアマネだより 7号(pdf)(2011.1)
ケアマネだより 6号(pdf)(2010.7)
ケアマネだより 5号(pdf)(2010.4)
ケアマネだより 4号(pdf)(2010.1)
ケアマネだより 3号(pdf)(2009.10)
ケアマネだより 2号(pdf)(2009.7)
ケアマネだより 1号(pdf)(2009.5)
精華町社会福祉協議会「居宅介護支援」における介護サービス情報を公表しましたのでお知らせします。
精華町社協では、要介護認定を受けられた方のケアプランを作成しています。
ご本人の心身の状況やおかれている環境に応じて、ご本人やご家族の意向をもとに介護サービスが適切に利用できるように、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が主治医やサービス事業者、施設等との連絡調整をします。
○利用できる方
介護保険で要介護の認定を受けた方。
○利用できる日時
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始はお休みです。)
○サービス内容
(1)ケアプランの作成(毎月の月間介護計画も含みます。)
(2)主治医やサービス事業者、施設等との連絡調整など。
(3)要介護認定などに関する各種手続きの代行など。
○利用料金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
○事業実施地域
京都府相楽郡精華町
○サービスの利用方法
まずは、お電話などでお申し込みください。
本会ケアマネジャーがお伺いいたします。
(TEL)0774-98-3398 (FAX)0774-98-3559